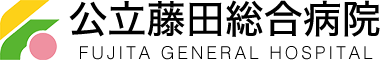令和6年度 公立藤田総合病院 病院情報の公表
病院情報とは
病院指標
病院の様々な機能や診療の状況などを具体的に数値化し示したものです。
病院指標を評価、分析することによって医療の質の向上をされることを目的としています。
医療の質指標
一般的に臨床指標と呼ばれており、病院の診療状況や実績など様々な指標を用いて具体的に数値化し示したものです。
指標の結果を把握・分析することで、病院の改善点が明らかになり、その結果医療の質が向上されることを目的としています。
目的
- DPCデータの質の向上
- DPCデータの分析力と説明力の向上
集計方法
- 各年度(前年4月1日~翌年3月31日)ごとの退院患者であり、一般病棟に1回以上入院した患者
- 入院後24時間以内に死亡した患者又は生後1週間以内に死亡した新生児は集計対象外
- 臓器移植(『厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件(厚生労働省告示)』に規定)は集計対象外
- 保険適用のデータのみ使用し、自動車賠償責任保険、労災保険、自費、新規高額薬剤使用の保険外データは対象外
- 患者数が10未満の場合は、『-』(ハイフン)にて表示
※患者数上位3位までが全て10件未満の診療科は掲載不要
集計項目
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
病院指標
年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 99 | 133 | 55 | 55 | 121 | 255 | 635 | 1,273 | 1,217 | 458 |
当院は、伊達郡および伊達市を中心とする県北地域における医療の中核病院として、地域住民の健康の保守・増進を図るため、当院の理念・基本方針を掲げ、地域に根ざした医療を行ってまいります。 その中で、少子高齢化、人口減少、経済状況の変化、保険制度改革など、医療を取り巻くさまざまな環境の変化に柔軟に対応し、地域包括ケアシステムの構築、各種疾病の早期診断、小児医療・救急医療・在宅医療の充実、各種疾病対策等により医療体制の推進を図ります。
年齢階級別の退院患者を見ると、0歳代は肺炎・気管支炎等の小児疾患、10歳代からは小児疾患の他、半月板損傷・靱帯損傷等のスポーツ外傷等の整形外科疾患が多く見られます。40歳代からは疾病の罹患割合が徐々に増加し、60歳代から90歳代までの患者数が、全体の8割程度を占め、肺炎・糖尿病・腎臓病・脳梗塞・心不全・がん・大腿骨骨折・腰椎圧迫骨折等、さまざまな疾患を治療しております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)のファイルをダウンロード
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 -手術なし-処置2:なし |
80 | 23.53 | 20.78 | 5.00% | 85.11 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) -手術なし-処置2:なし |
78 | 15.78 | 16.40 | 0.00% | 86.19 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 -手術なし |
31 | 21.00 | 13.66 | 3.23% | 81.65 | |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 22 | 22.00 | 10.26 | 0.00% | 84.41 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 -手術なし |
18 | 4.61 | 4.67 | 0.00% | 73.44 |
肺炎(特に誤嚥性肺炎)の治療を多く行っています。肺炎の治療は、ウイルス性か細菌性かを検査で特定し、それに合った適切な薬剤を用いて治療を行います。
尿路感染症は、尿道口から侵入した細菌が原因であることが最も多く、抗菌薬を投与して治療します。
また、全体的に平均在院日数が全国平均より長くなっているのは、寝たきりで高齢の患者が多く、退院後の自宅等での生活環境を考慮しケアマネージャーや地域サービス等と連携して退院調整を行っているためです。
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) -内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 |
152 | 3.16 | 2.57 | 0.00% | 70.00 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 -限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし |
72 | 11.76 | 8.88 | 5.00% | 80.17 | |
| 060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 -手術なし-処置2:なし |
28 | 10.32 | 8.51 | 0.00% | 78.49 | |
| 060335xx99x0xx | 胆嚢炎等 -手術なし-処置2:なし |
21 | 15.24 | 11.29 | 0.00% | 77.04 | |
| 060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 -手術なし-処置2:6あり |
20 | 3.72 | 4.64 | 0.00% | 70.06 |
当院は7名の消化器科医が常勤し治療にあたっています。
大腸ポリープに対する内視鏡治療の症例が最も多いです。ポリープはそのままにしておくと悪性化して癌になる場合がありますが、ポリープを切除してしまうことで大腸癌を予防することができます。
総胆管結石・胆管炎に対する内視鏡治療も多く行っています。結石が胆管を塞ぎ、細菌感染を伴うと胆管炎の状態になります。胆管炎は緊急性の高い病気で、時に急速に重症化し 命を落とす場合もあります。輸液や抗菌薬投与、内視鏡によるドレナージ等の治療を行います。
内視鏡治療は患者さんに負担があまりかからず、消化機能に障害を残さずに治療することができます。
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050130xx9900x0 | 心不全 -手術なし-処置1:なし-処置2:なし -他の病院・診療所の病棟からの転院以外 |
51 | 29.36 | 17.33 | 0.00% | 85.65 | |
| 050070xx9902xx | 頻脈性不整脈 -手術なし-処置1:なし-処置2:2あり |
– | – | 16.86 | – | – | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) -手術なし-処置2:なし |
– | – | 16.40 | – | – | |
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 -手術なし-処置1:あり |
– | – | 2.02 | – | – | |
| 050070xx99000x | 頻脈性不整脈 -手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし |
– | – | 5.64 | – | – |
心不全での入院患者さんが最も多くなっています。心不全の原因(高血圧症)となった疾患への治療も同時に行います。
また、不整脈に対する治療も行っており、不整脈には大きく分けて徐脈性、頻脈性の二種類に分けられます。頻脈性不整脈は脈が速くなる不整脈で、心臓がドキドキする、立ち眩み、めまい、けいれん、失神といった症状があり、最悪死に至る場合もある危険な不整脈です。
小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満) -手術なし-処置2:なし |
30 | 5.33 | 5.61 | 0.00% | 3.10 | |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 -処置2:なし |
21 | 3.43 | 5.55 | 0.00% | 6.57 | |
| 040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、 下気道感染症(その他) |
19 | 6.00 | 6.22 | 0.00% | 1.84 | |
| 030270xxxxxxxx | 上気道炎 | – | – | 4.71 | – | – | |
| 040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 -処置2:なし |
– | – | 6.98 | – | – |
当院で入院されている患者さんの多くは呼吸器系の疾患で入院されています。抗生剤、補液を行い早期に退院できるよう治療を行っています。
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) -ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 |
41 | 6.07 | 4.54 | 0.00% | 73.00 | |
| 060035xx99x5xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 -手術なし-処置2:5あり |
37 | 4.65 | 4.42 | 0.00% | 71.89 | |
| 060040xx99x4xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 -手術なし-処置2:4あり |
21 | 3.05 | 4.21 | 0.00% | 66.95 | |
| 060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 -結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 -処置1:なし-処置2:なし |
18 | 23.50 | 14.81 | 0.00% | 76.11 | |
| 060150xx99xxxx | 虫垂炎 -手術なし |
16 | 10.00 | 8.00 | 0.00% | 57.19 |
鼠径ヘルニアに対するヘルニア手術の症例を多く行っています。鼠径ヘルニアは臓器が足の付け根に飛び出してしまう病気で、鼠径部の膨らみが認められ違和感や痛みが生じることがあります。
次に直腸癌や結腸癌に対する手術、抗がん剤治療が多くなっています。当院にはがん化学療法専門の薬剤師が在籍しており、抗がん剤の副作用等の説明・指導や相談を受けることができ、患者さんが安心して化学療法を受けられる環境を整えています。
外科では、胆のう結石や胆のう炎に対して腹腔鏡下で行う胆嚢摘出術も行っています。腹腔鏡手術のメリットは手術創が小さいことです。開腹での手術では15cm~20cm程度お腹を切らなくてはいけませんが、腹腔鏡では数cmで済むため術後の創が目立たず、痛みも軽いため早期に退院することができます。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む) -人工関節再置換術等 |
143 | 27.01 | 21.38 | 0.00% | 73.76 | |
| 160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む) -腱縫合術等 |
92 | 17.72 | 12.71 | 0.00% | 25.00 | |
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 -人工骨頭挿入術 肩、股等 |
64 | 40.31 | 25.29 | 10.94% | 84.20 | |
| 070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 -手根管開放手術等 |
40 | 3.03 | 4.24 | 0.00% | 68.93 | |
| 070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 -その他手術あり-処置2:なし |
35 | 26.29 | 15.41 | 2.86% | 71.86 |
変形性膝関節症・変形性股関節症等には人工関節を置換する手術を行っております。人工関節手術では、手術を支援するロボット「Mako(メイコー)」を東北で初めて導入しました。精度の高い人工関節の設置、術後の痛み軽減、安全性の向上、合併症の低減、早期QOLの改善等が期待できます。
スポーツなどによる膝の靱帯や半月板損傷には、関節鏡視下による低侵襲な手術を積極的に実施しております。
転倒等により骨折した場合は、人工骨頭、釘、ねじ、プレート、ワイヤー等を用いて、骨折部を手術的に整復します。当院では、大腿骨や前腕の骨折の患者さんが多く入院加療されております。
整形外科とリハビリテーション部門とが密接に連携し、早期回復に向けた治療を行っております。
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 -手術なし-処置2:4あり-副病:なし |
48 | 31.29 | 16.89 | 6.25% | 77.21 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 -手術なし |
23 | 3.74 | 4.67 | 0.00% | 68.70 | |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 -手術なし-処置2:2あり-副病:なし |
21 | 35.10 | 16.94 | 0.00% | 80.71 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 -その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし |
16 | 8.00 | 9.83 | 0.00% | 83.94 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血種(非外傷性硬膜下血種以外)(JCS10未満) -手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし |
14 | 29.21 | 18.68 | 21.43% | 69.86 |
脳神経外科で入院が多いのは、急性期の脳梗塞の患者さん、めまいの患者さん等です。当院では最新のCT及びMRI設備がありますので、直ぐに画像検査を行い血管病変を特定し、薬物療法や手術の適応があれば血栓回収術を行います。 発症後4.5時間以内の場合、血管内の血栓を溶解する薬剤(t-PA製剤)を用いて治療を行う場合もあります。
また、めまいは耳から生じるものと脳から生じるめまいがあり、中には命に関わるものもあるため検査でめまいの原因を調べ治療を行っております。
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 -手術あり-片眼 |
178 | 2.00 | 2.49 | 0.00% | 76.07 | |
| 020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 -手術あり-片眼 |
– | – | 4.83 | – | – |
眼科では、白内障手術で入院される患者さんが最も多くなっています。
白内障手術は片眼ずつ1泊2日の入院で行います。両眼とも手術される場合は、2回入院する必要があります。
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 -手術なし-処置1:あり |
172 | 3.09 | 2.45 | 0.00% | 73.11 | |
| 110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 -前立腺悪性腫瘍手術等 |
38 | 14.11 | 11.11 | 0.00% | 70.47 | |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 -経尿道的尿路結石除去術-副病:なし |
26 | 7.54 | 5.16 | 0.00% | 67.27 | |
| 110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 -膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 |
23 | 8.39 | 6.75 | 0.00% | 77.26 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 -膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置2:なし |
23 | 9.09 | 6.81 | 0.00% | 77.30 |
泌尿器科では、前立腺生検を受けるために入院される患者さんが大部分を占めています。
前立腺生検とは、前立腺癌の有無を調べる検査です。生検によって癌が確定した場合、腹腔鏡や開腹による前立腺の摘出術を行います。現在は2024年に導入した手術支援ロボット「hinotori™」を使用した、より精密で低侵襲な手術を行っております。癌がなかった場合でも前立腺肥大症の症状がある場合には、経尿道的にレーザーを使用した切除術や水蒸気を使用した低侵襲な治療を行います。
膀胱癌で入院される患者さんも多く、経尿道的に行う手術(TUR-Bt)の症例が多くなっています。
腎臓内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎 ・慢性腎不全 -手術なし-処置1:なし-処置2:なし |
46 | 12.07 | 11.35 | 2.17% | 73.37 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) -手術なし-処置2:なし |
18 | 20.22 | 16.40 | 0.00% | 84.78 | |
| 110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎 ・慢性腎不全 -手術なし-処置1:なし-処置2:1あり |
13 | 24.62 | 13.75 | 7.69% | 70.62 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 -手術なし |
10 | 25.50 | 13.66 | 0.00% | 80.00 | |
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 -手術なし-処置1:あり |
– | – | 2.02 | – | – |
尿蛋や腎機能障害を認める慢性腎臓病は日本人の8人に1人が罹患している大変多い病気です。腎臓内科では、これらの慢性腎臓病(ネフローゼ症候群、IgA腎症などの慢性糸球体腎炎、糖尿病性腎症など)を中心に治療を行っています。随時、尿検査、血液検査、CT、MRI,腎生検により慢性腎臓病の確定診断を行い、福島県立医科大学附属病院とも連携し治療を進めています。腎臓内科の入院件数は、人工透析で使用する内シャントの狭窄または閉塞に対して、カテーテルを用いて再開通させる症例が最も多い件数となっています。人工透析とは、血液を身体から取り出し、機器を通じて血液をきれいにしてから身体に戻す治療法です。人工透析を受けている患者さんも年々増加しています。人工透析で血液を身体から取り出すために、腕の静脈と動脈をつなぎ合わせる手術を行います。これを内シャント手術と呼びます。
糖尿病による入院では、各種検査を行い、投薬などによる治療の他に、自宅に帰ってから糖尿病と上手に向き合っていただくために、自己管理するための知識や技術の習得を重く的とした「教育入院」を行っております。専門知識を持った看護師、薬剤師、検査技師、管理栄養士などの多職種の日本糖尿病療養指導士で構成されるチームで、患者さんの足の関節、服薬の確認、血糖測定方法、食事や運動に関する相談・指導を行い、糖尿病の合併症の予防や透析への移行の予防、フットケアなど取り組んでおり、また毎月5日間、チームによる糖尿病教室も開催しています。院内に設置されている糖尿病改善委員会が中心となり、糖尿病に関する様々な検討を行い活動しています。
麻酔科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | – | – | 9.33 | – | – |
麻酔科での入院は、帯状疱疹で入院される方がほとんどとなっています。
麻酔科は、他の診療科と連携して手術前後の診察や手術中の麻酔管理、椎間板ヘルニアに対する神経ブロック治療などがメインになっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数のファイルをダウンロード
| 初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | – | – | – | – | 35 | 21 | 1 | 第8版 |
| 大腸癌 | 18 | 10 | – | 48 | 82 | 73 | 2 | 第9版 |
| 乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 第8版 |
| 肺癌 | – | – | – | 14 | – | – | 1 | 第8版 |
| 肝癌 | – | – | – | – | – | – | 2 | 第6版 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
がんの進行度は「Stage(ステージ)」で表されます。ここではStage(ステージ)ⅠからStage(ステージ)Ⅳまでの4段階で分類しています。Stage(ステージ)Ⅳが最も 進行している状態です。Stage(ステージ)は様々な検査結果を総合的に判断して判定されます。その際に判断基準となるのが、がんの大きさ、周辺のリンパ節への転移の有無、遠隔臓器への転移の有無です。
当院での胃癌はStage(ステージ)Ⅰの治療が多く、内視鏡による切除を行っています。進行しているがんに対しては外科的治療を行っています。また、切除不能の患者さんに対しては抗がん剤治療を行っています。
大腸癌に関しても、早期がんであれば内視鏡による切除を行い、進行がんならば外科的治療を行っています。また、切除不能の患者さんに対しては抗がん剤治療を行っています。
肺癌に関しては、抗がん剤による治療の他、緩和(がんによる痛みを和らげる)治療等を行っています。
また、特定機能病院である福島県立医科大学附属病院と連携し、必要に応じて患者さんの紹介を行っています。
これらのがん治療は、専門の医師をはじめ、がん薬物療法認定薬剤師やがん看護認定看護師が中心となり、 チーム医療を推進し、診療ガイドラインに基づいた診断・治療を行っております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 15 | 8.80 | 65.20 |
| 中等症 | 89 | 17.38 | 80.31 |
| 重症 | 31 | 19.97 | 85.19 |
| 超重症 | 14 | 18.86 | 88.43 |
| 不明 | – | – | – |
重症度分類別に分類しており、 重症度が上がるにつれて在院日数も長くなる傾向があります。
肺炎の治療は、肺炎の原因となっている病原菌(細菌やウィルスなど)が何なのか見極め、それに合った薬剤(抗生物質など)を用い治療します。
脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| – | 109 | 34.27 | 78.86 | 6.42% |
当院における脳梗塞患者は、急性期における緊急治療が実施されております。
当院では、CT、MRI、脳血管撮影装置を導入しており、24時間体制での脳梗塞の検査、治療を行っております。また、2018年に最新のMRIとの入れ替えも行っておりより精密な検査を可能としております。
脳梗塞が見つかった場合、直ぐに薬物療法、適応があれば脳血栓の回収術を行います。また早期からリハビリテーションを開始し、社会復帰、家庭復帰が出来るようチームで医療を行っております。症状が安定してきた患者さんについては、地域包括ケア病棟にてリハビリテーションを継続し、社会福祉士、看護師を中心に、在宅復帰、介護老人保健施設、介護老人福祉施設等のケアマネージャー等と連携し、退院後安心して生活できるようサポートする体制をとっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)のファイルをダウンロード
消化器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・ 粘膜切除術(長径2㎝未満) |
146 | 1.01 | 1.06 | 0.00% | 69.80 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 41 | 1.53 | 9.53 | 1.43% | 82.01 | |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 (乳頭括約筋切開のみのもの) |
28 | 1.85 | 8.01 | 2.63% | 78.59 | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・ 粘膜切除術(長径2㎝以上) |
12 | 1.00 | 2.70 | 0.00% | 69.40 | |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 (早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) |
11 | 1.00 | 8.28 | 0.00% | 76.06 |
内視鏡による手術がメインとなっています。当院は消化器病学会及び消化器内視鏡学会の認定施設となっており、多くの内視鏡治療を行っております。
当院では内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術が最も多く、術後の出血等がなければ短期で退院されています。
次に内視鏡による胆道ステント留置術や乳頭切開術は、胆管結石の排石等に実施しています。また、手術不可の胆管腫瘍等の患者さんには、腫瘍によって閉塞する胆管にステントを留置するなどして、患者さんの生活の質を出来る限り下げないための治療を行っています。
早期胃癌に対しては内視鏡による内視鏡粘膜切除術を施行し、患者さんの負担にならないような手術を行っています。
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 41 | 1.61 | 3.42 | 0.00% | 71.27 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 26 | 2.04 | 5.35 | 0.00% | 68.35 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 16 | 3.69 | 18.50 | 0.00% | 74.94 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 14 | 1.07 | 4.14 | 0.00% | 35.43 | |
| K740-22 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | – | – | – | – | – |
鼠径ヘルニア手術が最も多くなっています。鼠径ヘルニアは幅広い年齢層に認める病気で、自然に治癒はせず手術が必要になる病気です。
そのほか外科での手術は腹腔鏡を使用した身体の負担が少ない手術方法が主流となっており、胆嚢摘出、癌切除、虫垂切除など幅広く腹腔鏡での手術を実施しています。
また、癌の患者さんで術後に再発の可能性が高いステージの場合、再発をできる限り防ぐため術後化学療法を行います。
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0821 | 人工関節置換術(肩、股、膝) | 153 | 2.23 | 24.98 | 0.00% | 73.80 | |
| K079-21 | 関節鏡下靭帯断裂形成手術 (十字靭帯) |
68 | 1.00 | 17.16 | 0.00% | 23.97 | |
| K082-7 | 人工股関節置換術 (手術支援装置を用いるもの) |
68 | 3.15 | 28.54 | 1.47% | 71.35 | |
| K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 51 | 3.26 | 39.10 | 7.84% | 84.43 | |
| K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) (椎弓切除) |
39 | 3.77 | 23.05 | 2.56% | 71.59 |
人工関節置換術を行うケースは、骨頭側だけで無く、関節窩の側にも破壊、変形、癒着などにより、動きが悪い、運動痛が強い、不安定で支持性が低いなどの障害がある場合であり、骨頭側と関節窩側の両方を入れ替えて、関節機能の再建を図ります。当院では、手術を支援するロボット「Mako(メイコー)」を東北で初めて導入しました。精度の高い人工関節の設置、術後の痛み軽減、安全性の向上、合併症の低減、早期QOLの改善等が期待できます。術後はリハビリを早期に行い、早期の日常生活動作自立、早期社会復帰を目指します。
関節鏡下靱帯断裂形成手術では、スポーツなどによる靱帯損傷の症例に対し実施される手術です。高度な技術を持った医師により、関節鏡下による低侵襲な手術を実施しております。
四肢の様々な部位の骨折に対する骨折観血的手術では、内固定材料として、鋼線、ワイヤー、プレート、ねじ、釘、ピンなど金属製のもののほか、合成吸収性プレート、スクリューなどを用い、骨癒合が起こるまでの間、骨折部の固定を行います。一定期間を経過し、骨癒合が得られた後には、抜釘術という固定材を取り除く手術を行います。
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 10 | 2.70 | 14.70 | 0.00% | 79.10 | |
| K164-5 | 内視鏡下脳内血種除去術 | – | – | – | – | – | |
| K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 (その他のもの) |
– | – | – | – | – | |
| K664 | 胃瘻造設術 (経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) |
– | – | – | – | – | |
| K1642 | 頭蓋内血種除去術(開頭して行うもの) (硬膜下のもの) |
– | – | – | – | – |
慢性硬膜下血腫に対する穿孔洗浄術が当院脳神経外科の手術で最も多くなっています。患者さんによっては、術後に慢性硬膜下血腫を再発する場合があり、繰り返し手術を行うこともあります。
眼科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術 (眼内レンズを挿入する場合) (その他のもの) |
178 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 76.07 | |
| K279 | 硝子体切除術 | – | – | – | – | – |
当院で主に行っている白内障手術は局所麻酔を行い、小さな傷口から水晶体を取り除き、人工の「眼内レンズ」を代わりに挿入する手術です。
手術時間は10~20分程度で、局所麻酔を行うため手術中の痛みはほとんどなく、傷口も小さく安全性の高い手術です。
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術) (電解質溶液利用のもの) |
43 | 1.28 | 6.09 | 0.00% | 77.33 | |
| K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 (内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
37 | 2.11 | 11.65 | 0.00% | 70.68 | |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 (レーザーによるもの) |
28 | 3.29 | 6.29 | 3.57% | 67.46 | |
| K841-7 | 経尿道的前立腺水蒸気治療 | 24 | 1.21 | 6.04 | 0.00% | 75.71 | |
| K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 21 | 1.57 | 7.00 | 0.00% | 67.67 |
泌尿器科では、経尿道的に膀胱内の腫瘍を切除する経尿道的悪性腫瘍手術(TUR-BT)を最も多く行っています。膀胱癌の再発などで手術を繰り返す患者さんもいるため、TUR-BTが多くなっています。また、アラグリオという薬剤を使用して、より膀胱癌の病変部分をわかりやすくして切除する手術方法を行う場合もあります。 腎の珊瑚状結石などの大きな結石には、経尿道的、経皮的アプローチの2つを同時に行うTAP(TUL assisted PNL)手術を施行しています。
2024年6月より前立腺癌を切除する支援ロボット「hinotori™」と前立腺肥大症を水蒸気で治療する「Rezum」が導入され、患者さんの治療の選択肢が増え、より高度な医療の提供が可能となりました。
腎臓内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 119 | 1.60 | 1.66 | 0.84 | 72.65 | |
| K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 (初回の実施後3月以内に実施する場合) |
28 | 0.07 | 1.57 | 0.00% | 68.79 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術) (単純なもの) |
– | – | – | – | – | |
| K616-7 | ステントグラフト内挿術(シャント) | – | – | – | – | – |
当院腎臓内科で行われる手術は、ほとんどが人工透析に関するものとなっております。
人工透析を行っている患者さんの中には、何度も透析シャントが詰まってしまい、繰り返し手術を行う方もいます。短期間で繰り返しシャントが詰まってしまう場合、ステントグラフトの留置が選択される場合もあります。
透析シャントの拡張、血栓除去術はほとんどが1泊2日の入院で行われ早期に退院することが可能な手術となっています。
その他 (DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
その他 (DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)のファイルをダウンロード
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 14 | 0.33% |
| 異なる | – | – | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 159 | 3.70% |
| 異なる | – | – |
播種性血管内凝固とは、がんや重症感染症などにより出血や多臓器不全となる重篤な病態です。
敗血症とは、生命を脅かすような重篤な感染症です。
その他の真菌症とは、免疫力の落ちた患者さんに起きる真菌感染症です。
手術・処置等の合併症とは、手術、処置が原因で起きた穿孔、感染症や、体内に挿入した人工物が原因で起きた病態です。外科的に作られた人工透析用の内シャントの閉塞もこの中に含まれます。
敗血症は、免疫力が低下していたり、特定の慢性疾患があると感染症が重篤化して発症しやすくなります。
当院における、手術・処置等の合併症については、透析を行っている患者さんの透析シャントの閉塞の症例です。
医療の質指標
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
リスクレベルが「中」以上の手術を執行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率のファイルをダウンロード
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 597 | 582 | 97.49% |
肺血栓塞栓症とは、肺静脈に血のかたまり(血栓)が詰まり、呼吸循環障害を引き起こす病気です。患者さんの状態や血栓の大きさによっては、ショックや突然死をきたし、予後不良となることもあります。この病気が発症する危険性が高い患者に対して肺血栓塞栓症の予防を目的として、弾性ストッキングやフットポンプを用いて、計画的な医療管理を実施しています。
血液培養2セット実施率
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 621 | 507 | 81.64% |
血液培養は、採血した血液中に存在する菌を育て検出する検査です。検出された細菌を明らかにすることで、感染症の全体像を知る手がかりとなり、治療に有効な抗菌薬を選択するための検査を進めることができます。
血液培養2セット実施率とは、血液培養検査において2セット以上採取された割合を示す指標です。血液培養は1セットのみの場合の偽陽性による過剰治療を防ぐため、2セット以上行うことが推奨されています。
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率のファイルをダウンロード
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 168 | 133 | 79.17% |
広域スペクトルとは、抗生物質や抗菌薬がさまざまな細菌に効果を発揮する性質を指します。抗菌薬が作用する細菌の種類を示したものを抗菌スペクトルといい、多くの細菌に効果がある場合は広域スペクトルといいます。広域スペクトルの抗菌薬は幅広い種類の細菌に効果が期待できるため便利です。しかし、過剰に使用すると薬剤耐性のない細菌を殺してしまうため、薬剤耐性菌のみが生き残る環境を作り出してしまいます。細菌培養検査を行い、適切な抗菌薬を選択し、使用につなげることが重要です。
当院では抗菌薬適正支援チームを組織し、上記のような抗菌薬の適正使用に関する取り組みを行っています。
転倒・転落発生率
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 76,086 | 245 | 0.32% |
入院という環境の変化によるものや疾患・治療・検査などの影響によって、入院中の転倒転落は少なくありません。転倒転落の指標として、①転倒転落発生率と②転倒転落が発生した際の損傷別の発生率を評価するものがあります。当院では、入院患者さんに対して、転倒転落のリスク評価を定期的かつ臨時にも行い、評価結果から危険度別の色分けのリストバンドの装着や、ピクトグラム(安全な入院生活のためにベットサイドに表示する絵ことば、絵文字)の活用、転倒転落防止のパンフレットの活用を行っています。ナースコールを押せない患者さんにはセンサー類の活用や被害軽減策マットを敷いて転倒転落による重症化対策を講じています。また、転倒転落対策チームが中心となって、多職種でラウンドし未然防止や再発防止に向けた活動を行っています。
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率のファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
|---|---|---|
| 76,086 | 3 | 0.003% |
転倒転落が発生した際には、速やかな報告制度によって組織内での情報共有を図っています。影響レベルの大きい事例には、頭部外傷や大腿骨骨折など命にかかわることや、日常生活動作能力や生活の質を低下することがあります。このため、影響レベル別の発生率を定期的に見ていくことに意味があります。損傷のある事例に対しては、応急処置や適切な処置はもちろんのこと、再発防止に向けて要因分析や多職種連携によるカンファレンスを行っています。このように転倒転落発生の低減も重要ですが、転倒転落による影響レベルの高い重症事例を防止していくことに努めています。
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率のファイルをダウンロード
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 912 | 910 | 99.78% |
手術後に、手術部位感染(Surgical Site Infection:SSI)が発生すると、入院期間が延長し、入院医療費が増大します。SSIを予防する対策の一つとして、手術前後の抗菌薬投与があり、手術執刀開始の1時間以内に、適切な抗菌薬を投与することで、SSIを予防できると考えられています。指標として手術開始1時間以内の予防的抗菌薬の投与率を示してSSI予防に取り組んでおります。
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率のファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 67,124 | 3 | 0.004% |
褥瘡は、看護ケアの質評価の重要な指標の1つとなっています。褥瘡は患者さんの生活の質の低下をきたすとともに、感染を引き起こすなど治癒が長期に及ぶことによって、結果的に在院日数の長期化や医療費の増大にもつながります。そのため、褥瘡予防対策は、提供する医療の重要な項目の1つにとらえられ、当院では、皮膚・排泄ケア認定看護師を中心に予防対策に取り組んでおります。
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合のファイルをダウンロード
| 65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 3,197 | 2,764 | 86.46% |
入院時に栄養状態を把握するために必要な評価となります。
身体的拘束の実施率
| 退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
| 62,847 | 5,318 | 8.46% |
身体拘束は、やむを得ない処置として行われる行動の制限であり、できる限り早期に他の方法に切り替えるよう努めなければならないものとされています。身体的拘束最小化チームが中心となり、身体拘束最小化の取り組みを行っております。
更新履歴
- 2025年09月30日 令和6年度 病院情報を公開しました。